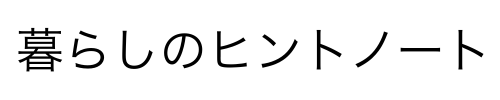オーディブルを利用して本を聴いているけど、内容が頭に入らない、集中して聴くことが出来ない。
そんな風に感じることはありませんか?
実は私もそうでした。
音は出ているけれど、何を言っているのかわからない。
ストーリーが理解できずに、そのまま終わってしまうという経験。
そこで今回は、オーディブルの内容が頭に入らない方への解決策を考えてみました。
集中して、聴く読書を楽しめるようになるにはどうすればいいのか、解説してみたいと思います。
これを読めば耳から聴く読書時間が、とても素敵で有意義な時間に変わるかもしれません。,
オーディブルが頭に入らない原因とは?

それではまず、なぜオーディブルの内容が頭に入らないのでしょうか。
その主な原因は何なのか、いくつか見ていきましょう。
音声だけだと集中しづらい
本を読むときは、文字を目で追ったり、行間を飛ばしたりと、自分のペースで調整できます。
しかしオーディブルは音声だけなので、耳から入ってくる情報をそのまま受け取る。
視覚的な補助がないぶん、頭の中でイメージを作りながら聴く必要があります。
それが集中力を奪ってしまうのです。
さらに、周囲の物音やスマホの通知など、外部刺激で意識が途切れやすいのも理由のひとつ。
結果として気づいたら話が進んでいて内容が分からない、という状況になりがちです。
文章を目で追う読書に比べて、オーディブルは頭に入りづらいと感じるかもしれません。
再生速度が合っていない
ナレーションのスピードが自分の理解スピードと合っていないと、頭に残りにくくなります。
たとえば、速すぎると追いかけるのに必死で理解が追いつかない。
遅すぎるとテンポが合わずに退屈して意識が飛んでしまう、といったことが起こります。
特にビジネス書や専門的な内容では、速すぎると重要なキーワードを聞き逃してしまいます。
逆に遅すぎると、集中が切れてしまいやすいのです。
つまり、速度がほんの少し合わないだけで、理解度や集中度に大きな差が出てしまうのです。
聴いている環境が合っていない
オーディブルはながら聴きができるのが魅力です。
しかし、環境が合っていないと内容がまったく頭に残らないことがあります。
人間の脳は複数のことを同時に処理するのが苦手です。
たとえば、通勤電車で周りが騒がしいと意識を奪われやすく、本の内容を集中して聴けません。
また、家事をしながらだと日常の思考が入り込み、気づけば話が大きく進んでいたということも。
興味が薄い内容を選んでいる
自分にとって興味のないテーマを選んでいませんか?
興味が薄い内容だと、聴いている最中に別のことを考え始めてしまいます。
気がそれてしまい、気づけば全然話が入ってこなかったという状態になりやすいのです。
人間の集中力は好き、知りたいと思うことに自然と向きます。
オーディブルを習慣にするなら、まずは自分が素直にワクワクできる本から始めるのがコツです。
興味があるテーマであれば、自然と耳が本の世界に集中し、理解も記憶もスムーズになります。
インプットだけで終わっている
オーディブルで本を聴くのに、インプットだけで満足してしまっていることがあります。
人間の記憶はただ聞いただけではすぐに薄れてしまいます。
紙の本のように線を引いたりページを見返したりできないため、流れていくままになりやすいのです。
実際、学んだ内容をしっかり定着させるにはアウトプットが欠かせません。
逆にアウトプットをしないままだと、曖昧な記憶で終わってしまうのです。
インプットとアウトプットをセットにすることで、聴いた内容がしっかり頭に定着していきます。
オーディブルが頭に入りやすくするための対策
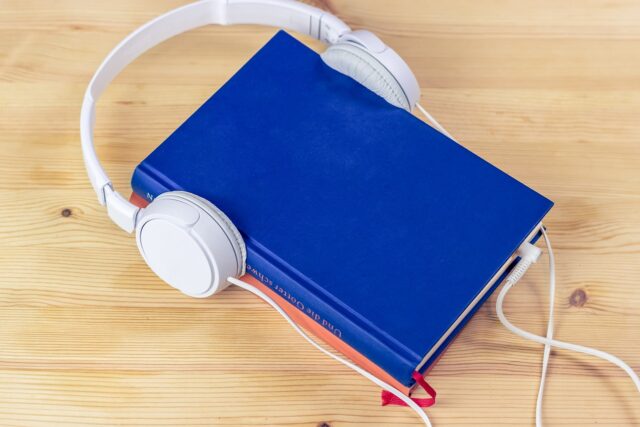
では、どうすればオーディブルの内容をしっかり記憶に残せるのでしょうか?
ここでは、記憶に残せる対策を解説していきたいと思います。
聴くだけではなく、重要なポイントをメモする
オーディブルを聞きながら、重要だと思ったポイントをメモしましょう。
人は聞いただけの情報よりも、手を動かして書いた情報の方が記憶に残りやすいと言われています。
メモといっても、丁寧にまとめる必要はありません。
気になったフレーズを一言書き留めたり、頭に残ったキーワードだけ書く程度で十分です。
紙のノートはもちろん、スマホのメモアプリや付箋に残してもOKです。
大事なのは聴き流さず、立ち止まって自分の言葉で整理することなのです。
聴くこととメモをすること。
このひと手間が頭に入りやすさを大きく変えてくれるのです。
再生速度を調整する
再生速度が自分に合っていない。
速度が速すぎると内容を追いきれず、大事な部分を聞き逃してしまいます。
また、逆に遅すぎるとテンポが合わずに眠気や退屈を感じてしまうのです。
聴く本のジャンルや、自分の集中度に合わせて速度を調整するのがポイント。
たとえば、物語や小説なら少し速め(1.2倍〜1.5倍)でも流れに乗りやすいですね。
専門書や自己啓発書のように考えながら聴きたい内容は、0.8倍〜1.0倍が理解しやすいです。
また、同じ人でも状況によって最適な速度は変わります。
大切なのは、標準速度にこだわらず、自分が一番集中できるスピードを見つけることです。
デフォルトのスピードが速すぎたり遅すぎたりする場合は、自分に合った速度に変更しましょう。
耳だけでなく目も使う(Kindleと併用)
オーディブルで聴きながらKindleで同じ部分を目で追う。
耳と目の両方から情報をインプットできるため、理解度と記憶の定着率がぐっと高まります。
文章の流れや構造を目で確認できるので、頭の中で整理しやすいのもメリットです。
さらに、集中力が切れてきたときも、文字を追うことで意識を本に引き戻せます。
逆に目が疲れているときは耳に頼れるので、状況に応じて切り替えられるのも便利です。
耳だけ、目だけに偏らず、両方をうまく使うこと。
そうすることで、オーディブルをもっと頭に入りやすい学びのツールに変えることができます。
シチュエーションを工夫する
オーディブルは、聴くシチュエーションによって頭への入り方が大きく変わります。
シチュエーションの工夫にはいくつか方法があります。
たとえば、朝の散歩中やジョギング中に聴けば、身体を動かしながら気持ちよくインプットできます。夜寝る前に布団の中で聴けば、落ち着いた気持ちでストーリーに没入できます。
家事をしながらなら、軽いエッセイや物語のように流して楽しめる本を選ぶと無理がありません。
集中して理解したいなら静かな環境で、気分転換やながら聴きなら軽めの内容で。
シーンに合わせて工夫するだけで、オーディブルはぐっと頭に入りやすくなります。
何度も繰り返し聴く
私たちの脳は、新しい情報を一度で完璧に覚えるのが苦手です。
むしろ、繰り返し触れることで大切な情報だと認識し、記憶に定着していきます。
最初はざっくり流れを聴き、二度目で重要そうな部分に意識を向けます。
そして三度目で自分の生活にどう活かせるかを考える。
このように段階を踏むことで、内容が自分の中に深く入ってきます。
一度きりで終わらせず、繰り返し聴くことこそが、オーディブルが頭に入るコツなのです。
アウトプットする
インプットした情報を、自分の言葉で表現するアウトプットが大事です。
耳で聴いただけでは、情報は一時的に頭に入っても、すぐに忘れてしまうことが多いのです。
アウトプットの方法は多様です。
聴いた内容をノートにまとめる、ブログやSNSで感想を書く、友人や家族に話す。
あるいは日常のタスクに取り入れてみる。
こうした行動を通じて、情報は自分の理解として整理され、記憶に定着します。
特に、誰かに説明するつもりでまとめると、内容の理解度がぐっと深まります。
さらにアウトプットは、気づきや学びを次の行動につなげる力にもなります。
自分の生活や思考に落とし込むことで、オーディブルの価値が最大化されるのです。
おすすめのオーディブル活用法

オーディブルをただ聴くだけでなく、記憶に定着させるための工夫や習慣化のコツをまとめました。
日常の時間を有効活用し、学びや気づきを最大化する方法をご紹介します。
短めの本から始める
オーディブルを習慣にするなら、まずは短めの本から始めるのがおすすめです。
長くて分厚い本をいきなり聴こうとすると、途中で内容を忘れてしまうことも。
また、集中力が途切れて挫折してしまうことがよくあります。
短めの本なら、短時間で最後まで聴き切ることができるので、達成感が得られやすいです。
また、短い本を何冊か繰り返すうちに、聴くスピードや集中できる時間、アウトプットの方法など、自分に合ったオーディブルの聴き方も自然と見つかります。
まずは短めの本で成功体験を積むことが、長期的な習慣化の第一歩になります。
小説よりもビジネス書・実用書を選ぶ
スーディブルを効率よく頭に入れるには、小説よりもビジネス書や実用書がおすすめ。
小説はストーリーを楽しむには最適です。
しかし、内容を記憶に残したり、実生活で活かすのは少し難しい場合があります。
一方で、ビジネス書や自己啓発書、実用書などは、具体的な考え方や行動のヒントが明確に整理されているため、聴きながらなるほど、使えると感じやすく、自然と記憶に定着します。
また、学んだことをそのままアウトプットしたり日常に取り入れやすいです。
そのため、知識を自分のものにしやすいのも大きなメリットです。
通勤・家事時間を活用する
オーディブルの大きな魅力は、手や目がふさがっている時間でも学びや読書ができることです。
通勤中や家事の時間など、ながら作業になってしまう時間を有効活用しましょう。
そうすれば、まとまった読書時間を確保しなくても知識を積み重ねられます。
ただし、ポイントは時間に合った本の選び方」です。
通勤電車や家事の最中は、専門書や難解な内容よりも、軽めの実用書やエッセイなど。
逆に集中して学びたい内容は、静かな時間にゆっくり聴く方が効果的です。
通勤や家事というスキマ時間を活用するだけで、着実に頭に内容が残る習慣に変わるのです。
実際に試してみた!効果があった聞き方の工夫

オーディブルをただ聴くだけでは頭に入りにくいと感じ、実際にいくつか工夫を試してみました。
その中で、理解や記憶に効果があった方法を具体的にご紹介します。
朝の時間の有効活用
早起きして、朝活メニューで15分の読書タイム。
朝は脳が最もクリアな状態で、集中力や記憶力が高まる時間帯です。
出勤前の30分や、家事前のちょっとした時間に聴くことで、効率的に情報を吸収できます。
朝は誘惑が少ないため、雑音や他の予定に邪魔されにくいのも大きなメリットです。
新鮮な時間に、これからの1日のスタートに、朝の時間帯を大いに活用しましょう。
通勤時間を有効活用
通勤時間は、毎日ほぼ同じ長さで確保できる貴重なスキマ時間です。
この時間をオーディブルに充てることで、1週間で数時間分の読書時間を確保できます。
満員電車の中でも耳だけで楽しめるため、紙の本よりも集中しやすい場合もあります。
さらに、往路では新しい内容を聴き、復路ではその日の内容を復習するなど、行きと帰りで役割を分けると記憶定着が格段にアップします。
寝る前のリラックスタイム
夜は一日の活動を終えて、心と体が落ち着く時間帯です。
このリラックスタイムにオーディブルを取り入れるましょう。
副交感神経が優位になり、落ち着いた状態で情報を受け取れます。
特に寝る直前は記憶の整理が行われるタイミングでもあります。
明かりを落とし、スマホやタブレットの画面は見ずに、イヤホンで聴くのがおすすめ。
睡眠導入にもつながり、心地よく1日を終える習慣になります。
軽い運動中のお供に
ウォーキングやストレッチ、軽いジョギングなどの有酸素運動中は脳の血流が良くなり、情報処理能力が高まると言われています。
このタイミングでオーディブルを聴くと、内容が頭に入りやすくなります。
特に、景色を見ながらの散歩や、ジムでのバイク運動中は手も目も自由になりますよね。
オーディブルを聴く環境としては最適です。
運動による気分の高揚も相まって、ポジティブな気持ちで内容を受け取れるのもメリットです。
家事などの合間の隙間時間に
掃除や洗濯、料理の下ごしらえなど、単純作業をしているときは手と目は動かしていても、脳には余裕がある場合が多いです。
この時間を活用してオーディブルを聴くと、生活の中に自然に学びや情報収集を組み込めます。
特に、繰り返しの動作やあまり思考を使わない作業中は、耳からの情報が入ってきやすくなります。
家事の終わりと同時に知識も積み上がるため、達成感も倍増。
気になる本があるけど、ページをめくって読むには時間がたりない、少しだけ読み進めたい、そんな時に耳から簡単に聴ける読書は重宝しますよね。
まとめ|オーディブルが頭に入らない原因を知って聴く読書を楽しもう
オーディブルが頭に入らない原因は、集中しにくい、スピードが合わない、環境が悪い、などさまざまですが、その時々のシチュエーションで、ちょっとした工夫で解決できます。
- メモを取る・再生速度を調整する・Kindleと併用する
- 聴く環境を整える・繰り返し聴く・アウトプットする
- 短めの本から始める・実用書を選ぶ
こうした方法を試しながら、自分に合った聴き方を見つけてみてください!
始めから理解しようとせずに、聞き流す気持ちで隙間時間を活用しましょう。
素敵な読書時間が出来ると人生も楽しく、新たな発見があるかもしれません。
オーディブルを上手に活用して、もっと効率よく学びを深めていきましょう!